OITA WEEKLY
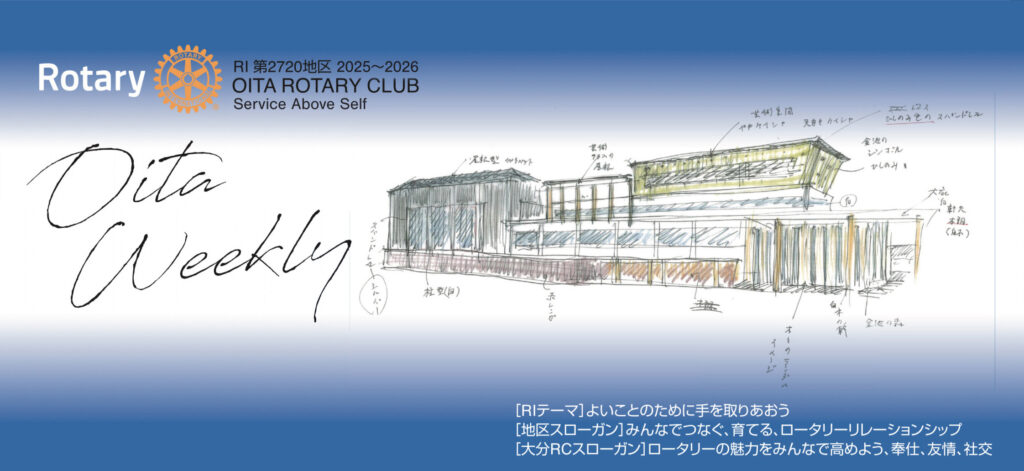
例会 毎週火曜日12:30 トキハ会館4F
会長 仲摩和雄 / 幹事 栗山嘉文
親睦夜間例会
於:ホテル日航大分オアシスタワー21階 エトワール
点鐘 18:30
ロータリーソング
それでこそロータリー
ゲスト・ビジター紹介
仲摩会長
会長の時間 仲摩会長
出席及び幹事報告
栗山幹事
委員会報告
ニコボックス 安德S.A.A.
今週のお祝い
【会員誕生日】
松本 淳也 会員 7月10日
懇親会
進行:クラブ管理運営委員会
| 会員総数(免除会員) | 48名(3名) |
| 出席総数(免除会員) | 31名(0名) |
| 出席率 | 68.89% |
| ゲスト | 5名 |
| ビジター | 4名 |
| 6月17日修正出席率 | 90.20% |
令和7年7月13日(土)第1回RA地区連絡協議会及びインターシティミーティング
10:30~15:00 コンパルホール
令和7年7月19日(土)~20(日)第1回米山部門セミナー
7月19日13:00 開会
7月20日 11:30 閉会(正午終了予定)
羽田多目的交流館(日田市)
令和7年7月26日(土)規定審議会報告会・クラブ活性化ワークショップ
12:30~16:40 ホルトホール大分
仲摩会長、佐藤信副会長、栗山幹事、今川副幹事、橋本均クラブ研修リーダー
令和7年8月2日(土)~3日(日)第41回インターアクトクラブ年次大会
2日12:00開会式
日本文理大学 湯布院研修所
須藤青少年奉仕委員長、西村IA担当
令和7年9月20日(土)大分OliOliロータリークラブ認証状伝達式並びに祝賀会
レンブラントホテル大分2階 二豊の間
17:00~18:00 認証状伝達式
18:20~20:00 祝賀会
仲摩会長、栗山幹事
| 開催日 | 内容 |
| 7月15日(火) | 上期クラブ協議会(全員協議会) |
| 7月22日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 7月29日(火) | 新井会員卓話 |
| 8月5日(火) | ゲスト卓話 山本 恒雄氏 (小説「由布山」著者) “最もよく奉仕する者、最も多く報いられる” |
| 8月12日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 8月19日(火) | 通常例会 |
| 8月31日(日) | 野外家族例会(8/26(火)の繰り下げ) 津久見・臼杵コース |
| クラブ名 | 開催日 | 会場 |
| 別府 | 7/11(金) | 両築別邸 |
| 大分東 | 7/17(木) | トキハ会館 |
| 大分南 | 7/18(金) | トキハ会館 |
| 大分1985 | 7/28(月) | トキハ会館 |
| 別府東 | 7/31(木) | ホテルサンバリーアネックス |
minutes
先週の議事録
今回は第1回目の会長の時間となりますので、私の自己紹介を簡単に致します。
生まれましたのは、1957年 昭和32年4月8日 大分県の臼杵市です。
父は、当時1919年創業の造船会社・(株)臼杵鉄工所に勤務する建築技師でした。
創業者である田中豊吉翁に可愛がられて、早朝しばしば自邸に呼び出され2人で朝食を共にし、仕事の打ち合わせをした後、社長車に同乗して出勤したり、田中社長のお供で臼杵駅から汽車を使って出張の際には田中社長は最前列から最後尾まで歩き知人顧客には必ず挨拶して廻り父に営業のやり方の規範を示してくれたそうです。
父は本当に田中社長の薫陶を受けた社員の一人でした。
父は建築技術者として臼杵や佐伯ときには神奈川県川崎まで遠征して、造船所建設の指揮をとっていたようです。
また臼杵の町の家老屋敷や土塀を修復したことを後年自慢していました。
当時、我が家は小さな社宅住まいでしたが、父の部屋のすわり机の上には建築の専門書と計算尺が置かれていたことが記憶に残っています。
私はそんなサラリーマン家庭の子供として幼年時代を臼杵の町で過ごしました。
臼杵湾に浮かぶ、おむすびのような島(津久見島といいます)の風景や、公園地と呼ばれ高台に位置する大友宗麟築城の臼杵城址でのお花見や運動会、唐人町という華やかな町家の商店街にある映画館の息子と友達になり、毎日のようにただでもぐり込んで見ていた日本映画の数々、夏は八坂神社の祇園祭、秋には紅葉の美しい白馬渓での紅葉狩り等々、楽しい思い出に満ち溢れていました。
そんなのほほんとした日々は長く続きませんでした。
昭和37年に父は(株)臼杵鉄工所を退社し、生まれ故郷の大分市鶴崎の地にて叔父夫婦と共に建築設計事務所を起業しました。
会社立ち上げの間、しばらく私は臼杵に残され父母とは別居、母方の祖母とまちなかの貸家でしばらく暮らしました。両親のもと小さいながらも庭付きの戸建てで、のんびり育った子供には生活環境の大変革でした。
1年ほどの別居生活を経てようやく新天地鶴崎で両親と暮らすようになりましたが、設計事務所と副業の青焼きサービスの作業所と家族の生活空間は一体の建物で、私は、仕事と私生活の区別ない環境で大人たちの仕事をする姿を見て育ちました。
毎晩遅くまで、父の製図板に向かって仕事をしている姿が記憶に残っています。
1964年、私は、大分市立鶴崎小学校に進学しました。
その頃大分市は、新産都の建設で活況に満ちあふれていました。
新日本製鐵 大分製鉄所建設工事を軸に40m道路の施設や明野地区の団地開発、新しい埋立地の増設、石油化学コンビナートの建設などに関わる地元の建設業も目の回る忙しさでした。
父の事務所も新日本製鐵の口座を開設することに成功し、明野団地の基本計画や屋内プールや新日鐵労働会館、新日鐵構内施設(鉄骨造)の設計や、殉職者の慰霊塔(チタン製)のデザイン設計等、実績を重ね会社は発展しました。
また、1964年は最初の東京オリンピックの年でした。
1年生の私たちも教室の天吊り白黒テレビでオリンピック観戦をしました。
私のお気に入りは体操の遠藤選手で、遠藤選手の真似事で鉄棒の練習をした記憶が残っています。
また当時の鶴崎小学校は地元中心商店街の子供と進出企業の社員の子供で児童の多くが占められており、割と都会的な雰囲気がありました。
1969年には、アポロ11号の月面着陸の映像を夏休みの最中、学校のテレビで見たことが強く印象に残っています。
それと、父親が連れて行ってくれた日本初の超高層ビル霞が関ビルの建設をテーマとした「超高層のあけぼの」という映画に深く感銘したのも覚えています。
自分の家の設計室にあるのと同じ製図板や手回しの計算機(当時パソコンはまだ無かった)を駆使して超高層ビルの設計に挑む建築士たちの姿が深く印象に残りました。
後年、霞が関ビルの設計に関わった人達と実際に出会うことになることは、次の機会にお話しします。
日時 2025年7月26日(土)
会場 (説明会)J:COM ホルトホール大分、(懇親会)レンブラントホテル大分
会費 懇親会:10,000円(当日、現地会場受付で徴収)
締切 7月15日(火)
参加希望者は幹事まで
松本淳也会員に仲摩会長から誕生日記念品が贈呈され、ご本人からコメントをいただきました。