OITA WEEKLY
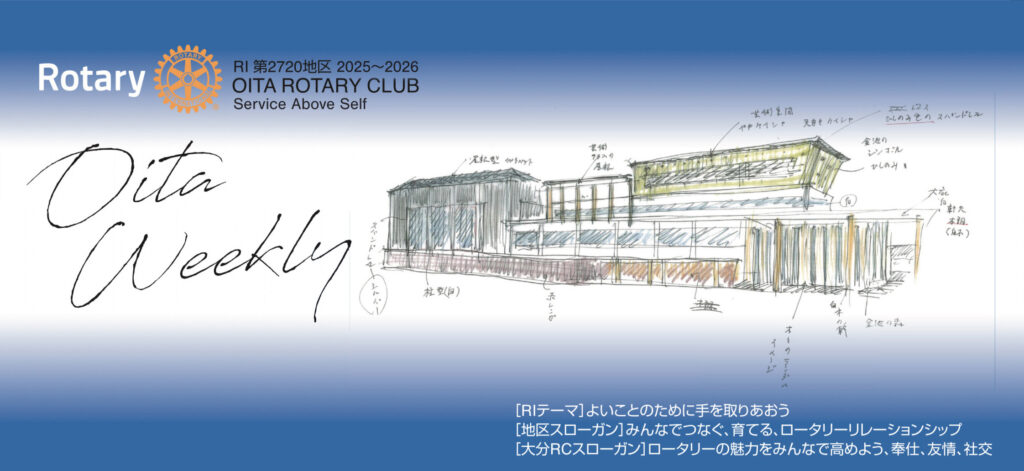
例会 毎週火曜日12:30 トキハ会館4F
会長 仲摩和雄 / 幹事 栗山嘉文
※食事12:20~12:40
点鐘 12:30
ロータリーソング
我等の生業
ゲスト・ビジター紹介
仲摩会長
会長の時間 仲摩会長
出席及び幹事報告 栗山幹事
新会員入会式
朝鍋 辰博 会員
矢野 剛史 会員
本田 勝也 会員
委員会報告
ニコボックス 安德S.A.A.
今週のお祝い
【会員誕生日】
廣原 武史 会員 7月18日
宮本 隆之 会員 7月19日
澤田 清 会員 7月25日
クラブ協議会(全員協議会)
新委員長より活動計画発表
| 会員総数(免除会員) | 48名(3名) |
| 出席総数(免除会員) | 22名(1名) |
| 出席率 | 47.83% |
| ゲスト | 2名 |
| ビジター | 9名(受付のみ) |
| 6月24日修正出席率 | 92.31% |
令和7年7月26日(土)規定審議会報告会・クラブ活性化ワークショップ
12:30~16:40 ホルトホール大分
仲摩会長、佐藤信副会長、栗山幹事、今川副幹事、橋本均クラブ研修リーダー
令和7年8月2日(土)~3日(日)第41回インターアクトクラブ年次大会
2日12:00開会式
日本文理大学 湯布院研修所
須藤青少年奉仕委員長、西村IA担当
| 開催日 | 内容 |
| 7月22日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 7月29日(火) | 新井会員卓話 “私と宮崎の紹介” |
| 8月5日(火) | ゲスト卓話 山本 恒雄氏 (小説「由布山」著者) “最もよく奉仕する者、最も多く報いられる” |
| 8月12日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 8月19日(火) | ゲスト卓話 尾野 賢治氏 (大分県副知事) |
| 8月31日(日) | 野外家族例会 (8/26(火)の繰り下げ) |
| クラブ名 | 開催日 | 会場 |
| 大分東 | 7/17(木) | トキハ会館 |
| 大分南 | 7/18(金) | トキハ会館 |
| 大分1985 | 7/28(月) | トキハ会館 |
| 別府東 | 7/31(木) | ホテルサンバリーアネックス |
| 大分南 | 8/8(金) | トキハ会館 |
| 大分東 | 8/21(木) | トキハ会館 |
| 大分1985 | 8/25(月) | トキハ会館 |
| 大分城西 | 8/27(水) | ホテル日航大分オアシスタワー |
| 大分南 | 8/29(金) | トキハ会館 |
| 職業分類 | 全国放送 |
| 所属委員会 | クラブ管理運営委員会 委員 社会奉仕委員会 委員 |
| 勤務先 | NHK大分放送局 |
| 役職名 | 局長 |
| 所在地 | 大分市高砂町2-36 |
| 勤務先電話 | 097-533-2801 |
| 勤務先FAX | 097-533-2805 |
| 創(開)業年月日 | 1941年6月20日 |
| 推薦会員 | 橋本 均会員 |
| 職業分類 | 光学製品配布 |
| 所属委員会 | クラブ管理運営委員会 委員 公共イメージ委員会 委員 |
| 勤務先 | 株式会社ヤノメガネ |
| 役職名 | 代表取締役 |
| 所在地 | 大分市中央町1丁目5-5 |
| 勤務先電話 | 097-536-5532 |
| 勤務先FAX | 097-532-5245 |
| 創(開)業年月日 | 1919年10月13日 |
| 推薦会員 | 橋本 均会員 |
| 職業分類 | 電気事業 |
| 所属委員会 | クラブ管理運営委員会 委員 公共イメージ委員会 委員 |
| 勤務先 | 九州電力株式会社 大分支店 |
| 役職名 | 執行役員大分支店長 |
| 所在地 | 大分市金池町2丁目3番4号 |
| 勤務先電話 | 097-537-8029 |
| 勤務先FAX | 097-537-8985 |
| 創(開)業年月日 | 1951年5月1日 |
| 推薦会員 | 梅林 秀伍会員 |
minutes
先週の議事録
今週も「建築を通して私が学んだこと」巡り会った人と建築をテーマに話しをさせて
いただきます。
1970年 私は大分大学付属中学校に進学しました。
進学のきっかけは、その年のお正月が明けてまだ3学期の始まる前、自宅で父親が
覚えたてのマージャンを家族相手に卓を囲もうとしていた時、突然鶴崎小学校の担任
古野先生が参考書をかかえて訪問してきました。そしていまにもマージャンを始めよう
としていた我が家族一同に「あなたたちは何をやっているのですか。この参考書で
和雄くんに勉強させて附属中学校を受けさせなさい」と一喝して帰って行きました。
その日以来、父親は2度とマージャン牌を握ることはありませんでした。
その後、私は附属中学校を受験し合格することが出来、鶴崎小学校の同級生と別れて
進学することになりました。
1970年は第1回目の大阪万博が開催された年でもありました。
残念ながら私は万博を見に行くことは家庭の事情で出来ませんでしたが、その万博の
マスタープラン、マスターデザインとお祭り広場の設計を担当したのが当時日本の
建築界のスーパースターである丹下健三でした。
丹下健三は、広島平和記念公園計画を皮切りに、東京都庁舎、香川県庁舎、草月会館、
東京オリンピック代々木屋内総合競技場、東京カテドラル聖マリア大聖堂、山梨文化
会館やユーゴスラビアのスコピエ復興計画や在日クウェート大使館等々、戦後の日本の
国家プロジェクトを次々と生み出し、国際的にも高く評価された最初の日本人建築家
でした。そして日本建築界の帝王であると同時に、昭和38年に新設された東京大学
工学部都市工学科の教授として数多くの建築家を育てた教育者でもありました。
丹下健三の設計は、20世紀のモダニズム建築を創造したル・コルビュジエの流れを組む
ものでした。丹下健三氏よりもやや先輩でパリのル・コルビュジエのアトリエで実際に
修業を積んだ前川国男氏や板倉準三氏のお2人と違い、彼は中学生の頃より建築雑誌に
掲載されたコルビュジエの作品で当時の最先端のモダニズムの建築を学びとりました。
彼は学生時代から飛び抜けた造形力を発揮し国の重要な設計コンペに勝利し、名声を
高めました。
丹下健三の設計手法は、縄文から弥生、伊勢神宮から寺社の伽藍配置に続く日本の伝統
的な様式と都市と建築の関係性に着目した都市計画的な視点を融合したものでした。
1970年の大阪万国博覧会計画には丹下のもっている建築思想が余すところなく発揮
されています。都市軸を中心に広がりのある全体計画、都市のコアとも呼べるお祭り
広場の設定、そしてそのお祭り広場を覆う大屋根を突き抜ける芸術家岡本太郎の太陽の
塔は、日本の縄文文化そのものの化身であり、丹下健三のとなえた「伝統と創造」を
体現したモダニズムの表現でした。
2025年の今日開催中の大阪万博では、日本の伝統工法である巨大な世界最大規模の
木造・木組のループが建設され、その中に会場が納められているというマスタープラン
ですが、同じ大阪万博のマスタープランが55年の時を経てこの様に変化したのかと
思うと感慨深いものがあります。
55年前の万博のテーマ希望にみちた「人類の進歩と調和」という言葉が思い出され
ます。
次回は、大分出身のもう一人の世界的建築家・磯崎新について考察したいと思います。
1. ガバナーノミニー・デジグネート候補者推薦について
地区より2028~2029年度ガバナーの推薦文書が届きました。
候補者推薦の提出期限は2025年9月19日(金)必着。
2.東北大学教授 講演会のご案内
大分1985ロータリークラブより地区補助金プロジェクトの一環として、東北大学より
講師を招聘し、講演会を開催するとのご案内が届きました。
日時 2025年8月29日(金)18時~19時
会場 トキハ会館6階 さくらの間
講師 東北大学医工学研究科 教授 新妻 邦泰氏
演題 脳を救う最前線~再生医療や創薬の可能性~
参加費 無料
参加ご希望の方は幹事まで
3.福井ロータリークラブ創立75周年記念式典及び祝賀会について
2025年10月25日(土) ザ・グランユアーズフクイ
記念式典 15:30~17:00
祝宴 17:30~20:00
会計監査 佐藤信彦会員
令和7年7月8日、収支決算書及び財産目録を監査し、適正であることを確認しました。
廣原武史会員、澤田清会員に仲摩会長から誕生日記念品が贈呈され、ご本人からコメントをいただきました。
各委員長より今年度の活動計画が発表されました。詳細は8月配布の会員必携をご覧ください。