OITA WEEKLY
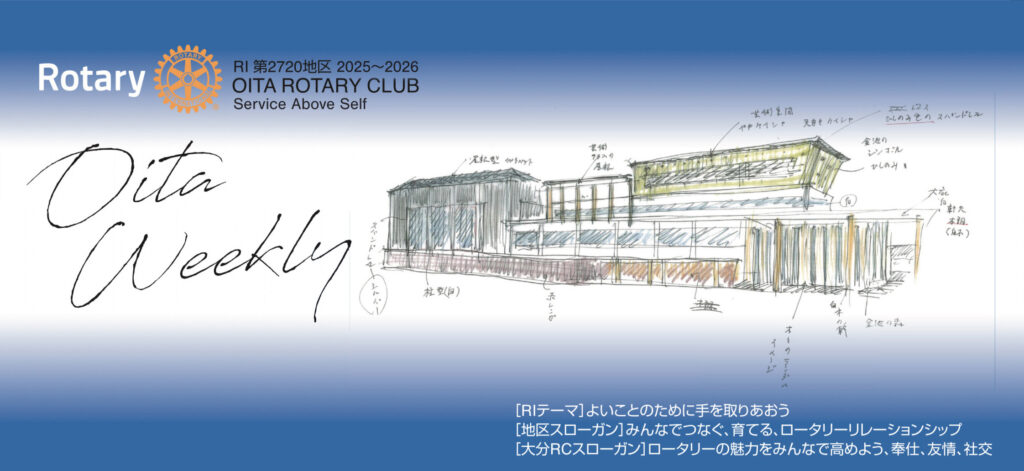
例会 毎週火曜日12:30 トキハ会館4F
会長 仲摩和雄 / 幹事 栗山嘉文
※食事12:20~12:40
点鐘 12:30
国歌 君が代
ロータリーソング 奉仕の理想
ゲスト・ビジター紹介 仲摩会長
会長の時間 仲摩会長
出席及び幹事報告 栗山幹事
委員会報告 関係委員長
ニコボックス 安德S.A.A.
今週のお祝い
【出席 100%】
橋本 仁 会員 28年
杉原 正晴 会員 12年
今川 尚俊会員 5年
須藤 礼会員 2年
【会員誕生日】
杉原 正晴会員 8月6日
卓話 13:00
「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」
小説「由布山」著者
山本 恒雄氏
| 会員総数(免除会員) | 51名(3名) |
| 出席総数(免除会員) | 38名(1名) |
| 出席率 | 77.55% |
| ゲスト | 0名 |
| ビジター | 2名 |
| 7月8日修正出席率 | 80.43% |
令和7年9月20日(土)大分OliOliロータリークラブ認証状伝達式・祝賀会
17:00~18:00 認証状伝達式
18:20~20:00 祝賀会
レンブラントホテル2階 二豊の間 仲摩会長、栗山幹事
令和7年10月4日(土)~5日(日)RI第2720地区ローターアクト第41回地区年次大会
4日 13:00~13:30 開会式
5日 11:10~11:40 閉会式
別府市公会堂
須藤青少年奉仕委員長
令和7年10月25日(土)福井ロータリークラブ創立75周年記念式典・祝宴
15:30~17:00 記念式典
17:30~20:00 祝宴
ザ・グランユアーズフクイ
仲摩会長、栗山幹事、福田会員、小野会員、須藤会員
令和7年10月25日(土)大分第4グループIM
14:00~16:00
平和市民公園能楽堂
令和7年11月9日(日)大分RC 第1回親睦ゴルフ
竹中カントリークラブ
| 開催日 | 内容 |
| 8月12日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 8月19日(火) | ゲスト卓話 尾野 賢治氏 (大分県副知事) |
| 8月31日(日) | 野外家族例会 (8/26(火)の繰り下げ) |
| 9月2日(火) | 石岡会員卓話 |
| 9月9日(火) | 夜間例会 ゲスト卓話 藤内 修二氏(大分県東部保健所長) ホテル日航大分オアシスタワー21階エトワール |
| 9月16日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 9月23日(火) | 定款第7条第1節に基づく休会 |
| 9月29日(月) | 藤田ガバナー公式訪問 (9/30(火)の繰り上げ) トキハ会館5階ローズの間 |
| クラブ名 | 開催日 | 会場 |
| 別府北 | 8/6(水) | ホテル別府パストラル |
| 別府東 | 8/7(木) | ホテルサンバリーアネックス |
| 大分南 | 8/8(金) | トキハ会館 |
| 大分東 | 8/21(木) | トキハ会館 |
| 大分1985 | 8/25(月) | トキハ会館 |
| 大分城西 | 8/27(水) | ホテル日航大分オアシスホテル |
| 別府北 | 8/27(水) | ホテル別府パストラル |
| 別府東 | 8/28(木) | ホテルサンバリーアネックス |
| 大分南 | 8/29(金) | トキハ会館 |
minutes
先週の議事録
先週に引き続き、私が中学生の頃、大分市で接した磯崎新の建築作品について話しをさせていただきます。
最初の作品は、磯崎氏の恩人であった岩田学園理事長・岩田正さんの為に作った岩田学園1号館・2号館と呼ばれる建物です。大きな片流れのシルエットが特徴的で舞鶴橋を渡る際に見えるこの建物は、岩田学園のランドマークとして現存する建物です。
岩田学園は、僕らが中学高校生の頃は家政学を教える女子高で、磯崎先生の設計による1号館・2号館以外は古い木造の建物でしたが、1980年代に岩田正氏のご子息である岩田英二理事長の代に学園が中高一貫の男子校に再編成され、その際にキャンパス全体を磯崎先生の設計で大改造しました。初期の1号館2号館を起点に1棟ごとに磯崎建築のエッセンスが表現され個性あふれる新しい教室棟、管理棟、体育館、ドミトリーなどを知的で秩序ある配置で処理し、岩田英二先生の目指すアカデミックな一流男子校の雰囲気を実現したキャンパスが生まれました。全盛期の磯崎アトリエのメンバーと構造家木村俊彦の手による素晴らしい建築群です。その後2016年に一棟だけ残っていた磯崎先生の設計によらない古い3号館の建て替えを現在の理事長であり、私の大学の建築学科の先輩でもある成瀬輝一先生から依頼があり弊社で手掛けることとなりました。
施工は岩田学園の卒業生たちの協力により竣工しました。
これは府内町のまん中に建っていた「N邸」と呼ばれる診療所兼住宅です。
1963年の作品で実質的な磯崎先生の処女作と言われています。一辺3.6m正立方体を4隅に配置した立方体を4本柱で持ち上げたピロティ形式の建物です。2階の大きな開口邸はガラスブロックで埋め尽くされ外部からの視線は完全に遮られています。屋根にも正立方体のトップライトが4個載せられ天上からの光を建築内部に落としています。
磯崎先生は師である丹下先生の作品からの脱却を目指していました。
ル・コルビュジェのモダニズム建築の日本における体現者であった丹下健三氏の一番弟子ともいえる磯崎先生ですが丹下健三の追求した日本的な美を取り入れた美しいプロポーションの構造美の建築を完全無視した4辺が同じ寸法の正立方体をモチーフとした最初の建築です。これは丹下健三との決別を意味するとも解釈できます。磯崎先生の建築には後年正立方体モチーフはしばしば登場します。
残念ながら、磯崎先生の処女作「N邸」は府内のまちなかから姿を消し、現存しません。
現在山口県秋吉台国際芸術村の一角に復刻再現されています。
次に大分県医師会館と旧大分県立図書館のお話をしたいのですが時間が大幅に超過しますので次回に回します。
1. リレー・フォー・ライフジャパン2025大分開催決定のお知らせがありました。
リレーイベントは2025年10月25日(土)~26日(日)
大分スポーツ公園 大芝生広場
(※大分RCは協賛金を出資予定)
2. 東北大学教授 講演会のご案内(再)
大分1985ロータリークラブ地区補助金プロジェクトの講演会ご案内を
回覧しています。参加ご希望の方はご記名いただくか事務局までお知らせください。
日時 2025年8月29日(金)18時~19時
会場 トキハ会館6階 さくらの間
講師 東北大学医工学研究科 教授 新妻 邦泰氏
演題 脳を救う最前線~再生医療や創薬の可能性~
参加費 無料
3.ガバナー月信 8月号(各テーブルで回覧)
ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
こども屋台選手権チラシ配布
杉原正晴会員に仲摩会長から誕生日記念品が贈呈され、ご本人からコメントをいただきました。
小説「由布山」著者
山本 恒雄氏
私は別府北ロータリークラブの山本恒雄と申します。
ロータリーに在籍して41年が経ってしまいました。
今回貴クラブでの卓話させて頂くことで改めて、ロータリーについて考える機会を頂きました。
さて、ロータリーの標語に、アーサー、F、シェルドンの(最もよく奉仕する者、最もよく報われる)があります。この(最もよく報われる)の意味はどういった事なのかと長い間漠然と考えてまいりました。
過日、我がクラブでのニコボックス申告の際に、ロータリー歴十年位の会員が次のように申告していました。
~自分の所属する業界のゴルフコンペが有り、その益金を市の社会福祉事業に寄付をしました。とても気持ちがよかったので、ニコボックスを申告します。~
この言葉を聞いて、成る程シェルドンの言いたいのはこれだなと私は納得したのです。
奉仕をすることによって得られる、心地よさ、爽やかさ満足感、これが報われるという意味だと感じたのです。
週一回の例会場や、地区大会等で会場に満ちている和やかな雰囲気。
これらはロータリーの奉仕のもたらす爽快感のなせる業であるのです。
私は、この春に八十一歳にして初めての本を上梓しました。そのお蔭と言いますか、不幸にしてと言うんでしょうか大学の後輩の当クラブ、前会長の山本先生に本日の卓話を頼まれる嵌めになりました。
(由布山)と命名した私の本は、今では全国的になっている湯布院観光発展の立役者三人、中谷健太郎、溝口薫平、志手康二さんらの行動と思考を端緒として、観光から町作りそして少しオーバーに言えば、生きる意味を考えた本です。そして、私が長い間所属しているロータリーの精神の実践を試みた本に結果として成ったようです。
この本の主人公は桑田司と言います。湯布院町に生まれ中学まで湯布院で学び、高校は大分市に通いました。
高校時代に出会った教師の勧めで、夏目漱石、芥川龍之介を読み始めます。これをきっかけに、読書は彼の生涯を通じた楽しみになるのですが、その下地は父親の愛読書の詰まった本棚と、そして長年父親が購読する新聞を読み続けていた事に在ります。新聞を読むことで蓄積された知識は彼の考え方を作り、その後広範な読書により人間性を確立してゆくのです。
司は東京の大学を卒業後暫く、丁度始まったマンション建設ブームにより、マンション販売の仕事に就きますが田舎町湯布院で育った彼には馴染める仕事ではありませんでした。数年後に妻の佐紀を連れ湯布院に帰り、名旅館(太古の湯)に勤め始めます。この旅館はあの(玉の湯)と社長の溝口薫平さんをモチーフとしています。
10年近く働いた後、司は仲間と語らって(湯布院の観光を考える会)を作り、又後年(湯布院の町を考える会)も作ります。中谷、溝口、志手の三氏の作り上げた(緑、静か、田舎)のコンセプトと、牛喰い絶叫大会、音楽祭、映画祭の企画の文化的雰囲気よって由布院観光は繁栄をつづけます。
私はこの牛喰い絶叫大会の感覚は一流のものだと思っています。多分中谷健太郎さんのものだと思います。
丁度、当時の寿屋現在のサントリーの開高健、山口瞳のキャチコピーのセンスと比肩するものです。
司達は観光の発展には、生涯をこの町で過ごす住人の協力と、住人の幸せな生活が不可欠であると考えを発展させたのです。観光の面では湯布院の最大の弱点である混雑を解消するために、郊外に大駐車場を作り町中に車の侵入をさせないようにし、又既存の駐車場は植樹をし湯布院の町中を増々緑豊かにして行きます。
町作りに関しては、(湯布院の町を考える会)を通じ、住民特に若い主婦を中心に、今日本が抱える社会問題を長い時間を掛けて学び続けます。
日本の抱える問題は人口減、少子化、高齢化、多額の借金等、数えれば限りないのです。そして一方、国連の毎年発表する幸福度の高い国のランキングは特に会員に良いヒントを与えてくれます。
スカンジナビア3国とスイス、アイスランドは例年この幸福度指数の高い国に入るのです。尺度となる項目には、GDPが有る程度高く, 教育の無料化が進み、ボランティア精神を国民が持ち、健康の維持、社会の寛容と腐敗の少なさなどが並んでいます。上記の5か国はその項目をかなり満足させています。こういった学びを通じ町民は湯布院の社会の在り方に関心を持ち、住民の投票行動に変化を与えます。自分達が納得できる町を作ろうと努力をします。その結果町から優秀な政治家が誕生するのです。
私の本の主要な登場人物には司の他に三人いまして、その一人は鈴木敏夫です。彼は島根県の津和野出身です。幼い時から母に教会に連れて行かれた所為なのか、ソクラテス的思考、真理を追究する考えを持っています。
敏夫は、若くして継いだ老舗の造り酒屋をバブル崩壊のあおりで倒産させてしまいます。そのショックから地元を飛び出して、ヨーロッパと日本を彷徨する旅に出、恵まれた環境に育った敏夫は初めて世間の厳しい現実を知るのです。
4年間のヨーロッパと日本の彷徨の果てに湯布院に辿り着き、仏山寺で禅の修行をさせて貰い、又湯布院の暖かい住民の支援にも支えられ倒産により負った傷を癒していきます。湯布院に定住した敏夫はその後、町長となり湯布院の町作りに貢献します。
もう一人、司の妻の佐紀は、東京のドレスメーカ―学院を卒業したデザイナーです。世界的に有名になった三宅一生やドレスメーカ女学院の先輩である島田順子を目標として努力を重ねます。こういった、一流のデザイナーはバックボーンになる哲学を持ち、佐紀はその影響をうけます。その後、湯布院でブチックを開きブランドを立ち上げ由布院駅前通りでファッションショウを開催したりします。その結果、湯布院はファッションの町になり田舎町に何軒ものブチックが誕生します。これは夫の桑田司の湯布院発展の町作りに協力した結果でもあったのです。
3人目は、東京の大塚にあるイタリアンレストランのオーナーシェフの松井慎一郎です。この松っさんはイタリア料理修業の為に大阪の料理学校を卒業後にイタリアを旅します。
彼はイタリア料理の勉強は無論、2年間の旅の間にイタリアとイタリア人に魅了されていきます。イタリアは日本人が一般的に考えているような軽薄な働かないイメージとは違い、長い歴史に裏付けられた重厚な思想と色んな人間を受け入れる許容力を持つ国でした。
松っさんのイタリア理解のきっかけは、羽田の国際線の出発ロビーの書籍店で買った一冊の本からでした。この本の作者、須賀敦子はイタリア文学者です。須賀は一般的ではないのですが本の愛読者はかなり多く、このクラブにも居られるかもしれません。須賀はイタリアに魅かれ29歳で渡航し長年イタリアを学び続けます。イタリア人の夫の死後は日本に帰国し、大学で教鞭を執り、イタリアの奥深い文化、人間を伝える著作を多く成しています。
これは余談になりますが、ロータリー第一回、国際奨学生で、後の国連難民高等弁務官に就任する緒方貞子氏と須賀敦子は聖心女学院で同級生であったことは、私には偶然とは思われないのです。
本好きの司と松っさんは、松っさんのイタリアレストラン(ミラノ)で知り合い長く交流を続けています。司は高校時代から読んだ芥川龍之介、夏目漱石を経て森鴎外の晩年の(寒山拾得)(高瀬舟)を読みます。私も年を取ってから森鴎外を読み強く惹かれる様になりました。司はヨーロッパの哲学に導かれた鴎外の日本的思想を理解してをり、松っさんの須賀敦子から学んだイタリア的思想、この二つの思想の合い触れる二人の語りは尽きることがません。
このように、主人公桑田司の思考は深まります。司を取り巻くこの三人は、湯布院の観光と町作りは欠かせません。
由布院観光は段々レベルを上げ、宿泊業に従事する若者の教育の為に(おもてなし研修所)の開設に至ります。儒教的(仁と礼)即ち思いやりと儀礼の考えをこの研修所では教えるのです。この儒教的思想は、私の年代は知っている様に、昭和の時代には日本に残っていて社会を穏やかにコントロールしていました。この、現在では失くしてしまった儒教的考え方を若者に教えるのです。
湯布院は、人口一万人で自治体の改革をするには適当な大きさだと言えます。
桑田司の通勤は自宅から(古代の湯)まで大分川沿いの道をスニーカーで歩いて20分、ゆっくりと四季の移り変わる由布山を見上げながら通います。若い頃に暫く働いた東京でのマンション販売の頃と大違いです。あの鋼鉄の高価な住まいを得るために一生働き続ける人達と違って、この田舎町湯布院では住民がお互いを労わって自然の中で暮らしています。
訪れた旅人はその町全体の優しい雰囲気に心を取り戻して束の間を過ごせるのです。
桑田司は55歳の時に湯布院ロータリークラブに入会しました。ロータリーの奉仕の理念は彼にとって正に目指す生き方であったのです。
冒頭に取り上げた、(最も奉仕する者、最もよく報われる)の考え方から、私は影響を受けてこの本を書いたのかも知れません。この本では主人公の桑田司と周囲の人たちの無償の働きが、湯布院の観光の繁栄と、湯布院の町の住みよさに貢献しているのです。
角度を変えて述べてみますと、
奉仕は、愛犬家、愛猫家が陥るペットロスに似ていると思いませんか。
手を尽くして可愛がった動物が亡くなると、飼い主は食事も喉を通らなくなり精神的にも落ち込みますが、一方動物は何も感じていません。何らかの感情を共有しているわけでもありません。しかし飼い主の悲しみの涙、追慕の気持ちは深く、この感情は人にとって精神的良い潤いなのです。結局人は動物に助けられているのです。
正に(最も奉仕する者、最もよく報われる)だと思います。
現実の世界は日々ひどい状態になって行っています。
そんな中、ロータリアンである我々はこの例会場に居る間だけでも、又ファイヤーサイドミーテイングを通じて変化する世界で、奉仕のバックボーンを確立して、自信を持ってロータリーの奉仕活動を続けたいと私は考えています。
この厳しい競争社会で我々は奉仕のお蔭で豊かな精神生活を送れるのだと思います。
現代社会の混乱は正にロータリー的思考を求めている様に私には思えるんです。
ご清聴ありがとうございました。